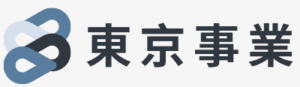2021/04/10 「インテリア ライフスタイル2021 先取りプレビュー」開催
公式ビジュアルウェビナー画面
メッセフランクフルト ジャパン(株)は、来る5月19日(水)〜21日(金)の3日間、東京ビッグサイト青海展示棟にて開催する「インテリア ライフスタイル 2021」に先駆け、来場予定者、およびプレス関係者向けに、同展のみどころを紹介する「インテリア ライフスタイル2021 先取りプレビュー」を、4月9日(金)に実施した。 「インテリア ライフスタイル」は、インテリア・デザインの新ブランドをはじめデザイン性、品質の高い最新トレンドアイテムが集結する最先端のデザイン見本市。昨年は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となったが、今年は2年ぶりに感染症対策を徹底し、東京ビッグサイト青海展示棟にて開催される。出展者数は6カ国・地域から412社を見込んでいる。 「インテリア ライフスタイル」の特徴は、出展商材やテーマごとに合わせた展示ゾーンが設定されている点で、今回は「HOME」「ACCENT」「KITCHEN LIFE」「JAPAN STYLE」「MOVEMENT」など12ゾーンが設けられ、それぞれ最新デザインアイテムが展開される。
「ETHICAL」
その中でも注目されるのが、新設された「ETHICAL」ゾーン。環境、人・社会、地球に配慮した商品が展示されるゾーンで、環境保全、アップサイクル、フェアトレード、障がい者支援、オーガニック、地産地消など持続可能な社会の実現を目的とした商品を扱う企業が集結する。「ETHICAL」に関連したトークショー「サステナブルとエシカルをもっと身近に」(5月20日(木)16時〜)、「経営・ブランド戦略とSDGsの関係」(5月21日(金)12時30分〜)も行われる。
また特別企画「Feel Good Working」では、オフィス以外に自宅やカフェ、ホテルなどボーダーレスで働く新しい働き方を提案する。
この他、新しい取り組みとして、デザイナーと地場メーカーをつなぐマッチングプロジェクト「Meet Design」も始動する。 「インテリア ライフスタイル2021 先取りプレビュー」では、「インテリア ライフスタイル」の特徴や各ゾーンの代表的な出展者を紹介、また会場内で実施する感染症対策を説明した。なお「インテリア ライフスタイル2021」への来場は事前登録が必要となる。
会場レイアウト
■出展ゾーン
ACCENT:デザイン雑貨、ギフト、ファッションアイテム
HOME:住まいの中心となる家具、インテリア雑貨、テキスタイル
KITCHEN LIFE:キッチン、ダイニング空間のための商材
EVERYDAY:豊かな暮らしの生活用品
MOVEMENT:トレンドを生み出すデザインブランド
JAPAN STYLE:日本のものづくり、伝統技術
JEWELRY:デザインジュエリー
ETHICAL(新設):環境、人・社会、地域に配慮した商品
Feel Good Working:気持ちよく働くための提案
NEXT:若手起業家による「商品化された新規ブランド」
TALENTS:新進デザイナーによる「商品化前のプロトタイプ」
FOODIST:ライフスタイルに溶け込む「食」の提案
ビジネス特集 デジタル庁 期待される民間の力 | IT・ネット
デジタル政策の司令塔となるデジタル庁が発足しました。行政手続きのオンライン化など、国や地方自治体のデジタル化を加速させることが狙いですが、デジタル改革が進むかどうかは民間の力も大きなカギとなりそうです。(経済部記者 永田真澄 / 猪俣英俊 / 加藤誠)
なぜデジタル庁?
なぜデジタル庁ができたのか?きっかけは、新型コロナウイルスをめぐる対応でした。
新型コロナの給付金の申請手続きなどを巡って、デジタル化の遅れによる弊害が浮き彫りになったのです。各省庁や自治体が、システムを別々に構築し、縦割りとなっているケースが多いことが背景にあります。
日本のデジタル化 待ったなし!
行政手続きのオンライン化や専門人材の配置といった状況から、各国の電子化の進捗を調べた国連の「電子政府ランキング」によると、日本の順位は14位。
日本のデジタル化は世界でも遅れをとっているのが現状です。こうした状況を抜本的に変え、縦割りを打破しようと作られたのがデジタル庁です。国や自治体のデジタル情勢に詳しい専門家は、日本のデジタル化は待ったなしの状況になっていると指摘しています。
野村 主任研究員「電子政府をやると言い始めたのは20年前でしたが、紙の書類で処理するのが当たり前で、手続きを根本から変える必要がありました。デジタル化は、効果がすぐに現れないと考えられていたため、あまり進みませんでした。この20年間を取り戻すために、民間の力をうまく活用しながら、ものすごいスピード感で取り組む必要があります」
デジタル化 暮らしが変わる?
600人体制でスタートしたデジタル庁。専門性の高いIT人材を確保するため、職員の3分の1にあたるおよそ200人を、IT企業など民間から登用しました。
民間の力も活用してバラバラだったシステムの仕様を標準化し、クラウド上で運用できる仕組みに作り変えることで、国と自治体の連携をスムーズにしシステムの維持管理費用を抑える計画です。
各市町村の負担が減り、税金や介護保険などの手続きでデジタル化が進めば、私たちが紙で申請していた児童手当や介護関連の申請もスマホからできるようになるといいます。
マイナンバーも活用し、銀行の口座情報などと連携させ給付金の支払いを迅速に行うことや、運転免許証との一体化を進め、マイナンバーカードでさまざまな手続きが行える社会を目指しています。
自治体のデジタル化 企業の支援も
私たちが住む自治体は、本当にデジタル化されるのでしょうか。小規模な自治体では人材も乏しいことから、どう進めればいいのか分からないという声もあがっています。こうした声に応えようと取り組む企業があります。
大手複合機メーカーのコニカミノルタは、デジタルに関する先進的なノウハウを自治体どうしが共有できるシステムを開発しました。自治体の行政手続きをおよそ4800通りに分類し、例えばある手続きをスマホによるオンライン申請ができるように変えたい場合、ほかの自治体がどのような手順で導入したのかを参考にできます。この会社では、NECやソフトバンクなどと連携し、自治体のデジタル化を支援したいとしています。
別府部長「このシステムを通じて、自治体が抱えるデジタル化の課題なども発信していきたいです。住民サービスを向上させるため、スピード感を持って取り組んでいきます」
公共データ開放で新ビジネス
今後デジタル化が進めば、企業側にとってもビジネスの可能性が広がりそうです。期待されるのが、国や地方自治体の情報が使いやすいデータの形で公開されることです。
例えば、国土交通省ではモデル事業として、立体地図データを一般に公開しています。これまで、役所内にとどまっていた地図データを、オープンデータにすることで、まちづくりのほか、アプリの開発など新たなビジネスに役立ててもらおうというのです。
ドローンの開発を手がける東京のベンチャー企業「A.L.I.Technologies」では、公開されている地図データを使って、都心などでドローンを使った物流サービスを実現しようと実験しています。
地図データが公開されたおかげで、現地に実際に行かなくても、ドローンの飛行ルートを作成することができ、運行に必要なコストや時間が大幅に削減できるといいます。現在、公開されているのは全国の56都市ですが、デジタル庁の発足で公開データがさらに増えれば全国各地でサービスを展開できると期待しています。また、飛行中に撮影したデータを地図にフィードバックし、最新の状態にアップデートすることも検討していて、官民が一体となってデータの価値を高める取り組みが行われる可能性もあります。こうした取り組みが進めば、ドローンが縦横無尽に飛び交い、物流の主役となるような未来が実現するかもしれません。
片野社長「地図データがなければ、どこを飛ばすか飛行ルートを作るため、現地での調査に膨大なコストがかかります。信頼性が高い国のデジタルデータを使うことで飛行の安全性が増し、物流などで新しい価値の提供につながる可能性が高まります」
デジタルデータで新たな価値を
国や自治体は、このほかにも避難所や防火水槽といった防災関係のデータなどもすでに公開していて、デジタル庁の発足を機に、民間企業などによるデータの有効活用がさらに進むことが期待されています。
今後、デジタル庁は、法人や土地、インフラ、交通、気象といった分野で、国などが持っているデータについて、規格やルールなどを統一し、社会の基幹となるデータベースをつくる計画です。「21世紀の石油」とも呼ばれるデジタルデータは、競争力や価値の源泉とされ、各国がしのぎを削っています。データの利活用をいかに進めるかが私たちの暮らしや経済の活力に直結するだけに、デジタル化は待ったなしの状況です。ただ、個人情報の保護や、サイバーセキュリティなどに対する懸念もあります。また、民間の力を活用することから、システムを調達する際に所属していた企業に対して便宜供与が行われないかなど、公平性や透明性の確保も課題となります。
デジタル化の遅れを挽回するために、デジタル庁にはこうした懸念に対応しつつ、司令塔役として改革を断行する強力なリーダーシップが求められると専門家は指摘しています。
日本総合研究所 野村敦子主任研究員「日本はデジタル化が遅れていますが、逆に世界の成功事例を取り入れやすい面もあります。デジタルデータは社会課題を解決したり、新しいサービスを生み出したりする大きな可能性があります。デジタル化は一丁目一番地の重要課題で、デジタル庁には旧態依然とした規制や慣行を打破する役割が求められていると思います」
経済部記者永田 真澄平成24年入局秋田局や札幌局を経て現所属総務省や情報通信業界を担当
経済部記者猪俣 英俊平成24年入局函館局や富山局を経て現所属電機メーカーを担当
経済部記者加藤 誠平成21年入局帯広放送局を経て現所属情報通信業界を担当
伊藤忠商事/リニューアブルディーゼルタンクローリー使用開始 ─ 物流ニュースのLNEWS
伊藤忠商事、伊藤忠エネクス、INPEX、INPEXロジスティクスの4社は、再生可能資源由来燃料であるリニューアブルディーゼル(Renewable Diesel、以下「RD」)の日本初となるタンクローリー車での使用に係る協業に着手したと発表した。
<リニューアブルディーゼルを使用するタンクローリー>
これにより、INPEXロジスティクスは、伊藤忠商事が世界最大のリニューアブル燃料メーカーであるNeste OYJから調達し、伊藤忠エネクスが供給するRDを、北陸・甲信越地方で国産原油及び石油製品の輸送を担う18台のタンクローリー車の燃料として使用する。同地域でのRDの利用並びにタンクローリー車でのRD使用は日本初となる。
この取組に先立ち、伊藤忠商事はNesteとRDの日本国内向け輸入契約を締結、伊藤忠エネクスは国内のRD輸送及び給油に係る一連のサプライチェーンの構築を行った。この取組は、これらにINPEXグループが既に確立している北陸・甲信越地方を中心とした販売網を組み合わせることにより実現したもの。
今後4社は、INPEXロジスティクスが保有するタンクローリー車への継続的なRD供給及びその使用により、陸上輸送分野での脱炭素化を牽引していく。また取組を通じて、INPEXグループが有する北陸・甲信越地方を中心とするネットワークを活かしたRDのビジネス展開に向けた協働を進め、共にサーキュラーエコノミー及び脱炭素社会の実現に寄与することを目指していくとしている。
なお、NesteのRDは食品競合の無い廃食油や動物油等を原料として製造され、ライフサイクルアセスメントベースでのGHG排出量で石油由来軽油比約90%の削減を実現。RDは主に輸送用トラック・バス等で使用され、所謂「ドロップイン」燃料として、既存の車両/給油関連施設をそのままに利用開始することが可能で、既に欧米を中心に広く流通実績がある。脱炭素施策に係る導入コストを最小限に抑え、GHG排出量削減にも大きく貢献できる次世代リニューアブル燃料として、今後の陸上輸送分野での更なる利用拡大が期待される。
...
ビジネス特集 日本の“石油王”が夢みた世界 | NHKニュース
国内最大規模のガソリンスタンド網を経営しながら、石油需要が半分に減ってしまうという衝撃的な見通しをもとに戦略を立てようとした異色の経営者のお別れ会が、ことし5月、開かれた。石油元売り大手「ENEOSホールディングス」名誉顧問の渡文明だ。石油元売り会社の再編に数多くかかわり、記者たちからは「石油王」と親しみを込めてそう呼ばれていた。石油全盛の時代を生き抜き、まさに激動の脱炭素の時代を迎えるいまこそ、常に先を見続けていた渡ならどんな経営戦略を打ち出したのか。聞いてみたかったのは私1人だけではないはずだ。※敬称略(経済部記者 永田真澄)
厳しさと明るさと
渡とはどんな人物だったのか。ENEOSホールディングス会長の杉森務が取材に応じた。
杉森会長「とにかく仕事に厳しい上司だった。渡さんが常務になった時、常務会の当日は、朝早く来て待機してろと言われた。直近の販売動向についてレクチャーしろということで、めちゃめちゃ詳しいし細かい。下手なレクチャーをしたら、細かいところまで突っ込んでくるので緊張感があった」
渡はせっかちだったという人は多い。レクチャーする杉森も神経をとがらせて準備しただろう。一方で杉森もよくゴルフを一緒にやったりお酒を飲んだりしたと語るように親しみやすい性格でも知られた。記者に対してもざっくばらんに話しかけ、当時、経営の新たな柱にしようと取り組んでいた「太陽電池」、「蓄電池」、「家庭用燃料電池」の事業を「電池3兄弟」と名付けてみずから積極的にアピールしたりした。その渡の力が最も発揮されたのが業界再編だとされる。
業界再編の中心に
渡が勤めた会社の名前は何度も変わった。1960年に「日本石油」に入社したのち、「日石三菱」、「新日本石油」、「JXホールディングス」、「JXTGホールディングス」、そして現在の「ENEOSホールディングス」。業界第2位だった日本石油は1999年に三菱石油と合併して「日石三菱」となり業界1位となったが、役員としてこの合併に深く関わった。
翌年、渡は社長に就任。さらに2010年には、JOMOブランドのガソリンスタンドで知られたジャパンエナジーを傘下に持つ新日鉱ホールディングスとの経営統合を主導。社名をJXホールディングスとした。その後、会社は2017年に業界3位の「東燃ゼネラル石油」と統合した。その「先見の明」を杉森は回想する。
杉森会長「石油の需要が半減する時代に備えて、経営資源を何に振り向けるか。業界再編は生き残り戦略でもあるし、将来の大きな構造改革のためにも必要だった」
積極的な再編戦略を推進する渡は担当記者たちからは「石油王」と呼ばれるようになっていた。その次の一手を多くの経済記者は固唾をのんで見守った。
渡氏「次はうちと大手電力会社、大手ガス会社の3社統合で総合エネルギー企業だ」
具体的な社名をあげて渡が本気か冗談か分からない統合構想をぶちあげるのを聞き、あっけにとられた記者は少なくない。
環境問題に向き合って
渡を業界再編へと突き動かしたもの、それは石油業界冬の時代への強い危機感だった。1997年、「京都議定書」が採択。先進国に二酸化炭素の排出削減が義務づけられたのだ。さらにハイブリッド車の普及とともに自動車の燃費がどんどん向上し、国内の石油需要は1999年度から減少に転じていた。ちなみに2019年度の石油需要はその時の3分の2まで落ち込んでいる。
渡の「先見の明」を象徴する真骨頂の出来事がある。2003年、当時の東京都の石原慎太郎知事が軽油に含まれる硫黄分を首都・東京の大気汚染の原因として問題視。独自のディーゼル車の規制を実施した。石原が黒いすすの入ったペットボトルを手に訴える姿を記憶する人も多いだろう。新日本石油の社長、そして業界団体「石油連盟」の会長だった渡はすぐさま動いた。生産コストの上昇を伴う環境への対応は業界としては簡単なことではない。しかし業界に呼びかけ、研究開発や設備投資に全体として数千億円規模の投資を実施。従来の計画を2年から3年も早める形で「サルファーフリー」と呼ばれる有害な硫黄分をほとんど含まない軽油やガソリンの全国販売を決断した。
報告に訪れた渡に対し、石原は「英断に感謝する」とたたえたという。その後「水素の時代が来る」と、脱炭素にかじを切っていく。
「格好いい」エネルギー
渡が2010年に著した本のタイトルは『未来を拓くクール・エネルギー革命』。「クール」つまり「格好いい」エネルギーとは渡によると水素のことだ。水素は脱炭素時代のエネルギーの本命候補の1つだとされる。自動車の燃料のほか、航空機、それに火力発電の燃料として、今、各国が本格的な技術開発に乗り出そうとしている。渡はガスから水素を取り出して発電する「燃料電池」の事業化に特に力を入れた。
杉森会長「渡が『水素だ』と言っても当時は業界内でも社内でもピンと来ていなかった。それが渡の鶴の一声でまずは家庭用の燃料電池事業を一気に立ち上げることになった。結局、採算がとれず、私が社長になってから家庭用燃料電池事業からは撤退することになった。それでも渡からは『水素は絶対にやめるな。必ずこれから主役になる。水素の時代が来る』と言われた」
渡のメッセージ
渡は、晩年、みずからの母校、成城学園で理事長を務め、教育にも力を入れた。今回、教育についての情熱がほとばしるような手書きの文書を入手した。少子化が進み、教育現場にも厳しい荒波が押し寄せる中でどうやって学園が生き残っていくのか。みずから書きつづったメモだという。思いがほとばしるような筆致で書かれた数々のことばがあった。「時代の要請する人材」として「社会を変え未来を創造する人材」だと言い切っていた。また「既存の概念や周囲の環境にとらわれずこれまでにない発想で物事を変えていく力」とも書き記している。学園の幹部たちは、この文書にあるひと言ひと言に込められた意味に思いを巡らせながら学園について議論したという。その中にこんなことばを見つけた。
「自分の信じる道を自ら切り開くことが社会発展の原動力となる」時代を読み、先見の明を示し続けた渡が残したメッセージ、私も胸に刻みたい。
経済部記者永田 真澄平成24年入局秋田局や札幌局を経て経済部経済産業省やエネルギー業界を取材。
香港:イオンがコメダ珈琲店をオープン | 海外ビジネスニュースを毎日配信!− DIGIMA NEWS
香港:イオンがコメダ珈琲店をオープン
イオンは飲食事業への参入として日本の喫茶店ブランドである「コメダ珈琲店」を香港に誘致し、10月21日に1号店を黄埔のイオンスタイルにオープンする。
この記事の続きを読む
20日付香港各紙によると、イオンはコメダと地域フランチャイズ経営協定を交わし、長期的に大中華区に100店のコメダ珈琲店を開設する計画で、香港で3年以内に少なくとも10店舗をオープンさせるという。 早ければ来年上半期に2、3号店をオープンする。粤港澳大湾区では深セン市などに進出する。香港のコメダ珈琲店の商品価格は日本の1.5倍となり、メニューは完全に日本のメニューに合わせているほか、わずかながら現地化して香港市民の口に合うようにしている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■記事提供 「香港ポスト」
■日刊香港ポストへの登録はコチラから【購読無料】月曜から金曜まで配信 / ウェブ版に掲載されないニュースも掲載※hotmail、outlook、icloud、http://me.com は現在のところ配信されにくいので、ご注意ください※メールアドレスの入力ミスにご注意ください※香港ポストからのお知らせやマーケティング情報が配信される可能性があります
]]>
この記事の提供会社
「香港ポスト」 香港と中国本土の政治・経済・社会ニュースを日本語で速報します
https://hkmn.jp/
キユーピー 主力のマヨネーズ4月から値上げへ 卵価格急騰 | NHK
大手食品メーカーの「キユーピー」は、鳥インフルエンザの感染拡大の影響や、飼料の高騰で、卵の価格が急騰しているなどとして、主力商品のマヨネーズなどをことし4月から値上げすると発表しました。
発表によりますと、値上げの対象となるのは、家庭用ではマヨネーズ類やタルタルソースなど合わせて36品目で、参考小売価格でおよそ3%から21%引き上げます。代表的な「キユーピー マヨネーズ」の450グラム入りの商品の場合、税込みで、これまでの475円から520円に引き上げられます。また、業務用では、マヨネーズ類や卵の加工品合わせて259品目について、出荷価格でおよそ1%から17%引き上げるとしています。いずれも、ことし4月1日の出荷分から値上げされます。理由について会社では、鳥インフルエンザの感染拡大や飼料の高騰を受けて、卵の価格が急騰しているうえ、さまざまな原材料価格や資材費などの上昇が続いているためだとしています。卵をめぐっては、コンビニエンスストア大手のセブン‐イレブン・ジャパンが1月31日、鳥インフルエンザの流行で供給が滞っているとして、卵を使った一部商品について販売を休止したり、卵の量を減らしたりするなどの対応をとっていて、影響はさらに広がりそうです。
ひとことで株価を動かすウォーレン・バフェットが次に狙う日本株 – 経済・ビジネス – ニュース|週プレNEWS
先日来日したウォーレン・バフェット氏。ジョージ・ソロス、ジム・ロジャーズと共に世界三大投資家に数えられる。1930年生まれの御年92歳。ちなみに、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツとは仲良しである世界三大投資家のひとりが、まさかの来日。おまけに「日本株への追加投資をするかも」なんて言うもんだから、相場は大騒ぎ!! 投資した企業がその後軒並み高騰するバフェット氏が、次に狙う企業を識者に聞いた。* * *■バフェットは何しに日本へ?〝投資の神様〟とうたわれるウォーレン・バフェット氏(92歳)が、4月上旬に来日した。投資をしない人にはなじみの薄い名前かもしれないが、世界的に影響力を持つアメリカ人投資家で、約14兆円の資産を持つ世界5位の大富豪でもある。バフェット氏は常々米国の強さを語り、投資先も米国企業がほとんど。そんな彼が、わざわざなぜ日本に?その理由は、彼が日本への投資を拡大しようとしているからだ。さかのぼること3年前、バフェット氏は自身がCEOを務める投資会社バークシャー・ハサウェイ(以下、バークシャー)を通して、日本の五大商社(三菱商事・三井物産・住友商事・伊藤忠商事・丸紅)の株式を取得したことを明かした。以来、各社の株価は軒並み上昇し、丸紅に至っては3倍以上に! バフェットはおそらく、日本への投資拡大というアイデアに自信を深めたことだろう。総合商社は海外との資源取引に強みを持っている。コロナ禍とウクライナ戦争が引き起こしたエネルギー危機により、日本の大手商社はここ1年で莫大(ばくだい)な利益を上げたわけだが、バフェット氏はまるでそのことを1年前に読み切っていたかのようだ。来日時には「日本株へのさらなる追加投資を検討している」との発言も飛び出したが、彼は果たして今後、どんな会社に手を伸ばすのか?核心に迫る前に、バフェット氏の足跡を簡単に振り返ろう。三井不動産の東京ミッドタウン八重洲。都心に優良な物件を保有する同社はバフェット氏好みの銘柄といえる■シンプルすぎるバフェットの投資法バフェット氏はいかにして大富豪となったのか。その答えは驚くほど単純で、投資の成功をひたすらに積み重ねたのだ。物語のスタートは1965年。34歳のバフェット氏は、当時繊維会社だったバークシャーを買収すると、事業再建に着手する。CEOに就任してからは事業を転換し、保険会社や菓子メーカー、電力会社、鉄道会社などさまざまな企業の買収と、優良企業への株式投資を進めたのだ。その結果、58年間でバークシャーの株価はなんと約3万8000倍に成長。当時バークシャー株を1万円分買っていたら、今頃資産額が4億円に迫る大金持ちになっていたわけだ。では、バフェット氏はなぜ50年以上勝ち続けることができたのか? その秘訣(ひけつ)は「よい株を安く買い、長く持つこと」だという。この理屈で彼はコカ・コーラの株式を34年、アメリカン・エキスプレス(アメックス)の株式を29年にわたって保有し続け、巨額の配当を得ている。また、自分に理解できないビジネスには見向きもせず、「10年間持ち続けられない銘柄は10分間ですら持とうと考えてはいけない」と彼は言う。だから、バークシャーはコロナ期間中に株価が暴騰した後、たちまち暴落してしまったハイテク銘柄には見向きもしなかったし、AI株についても「私はわからない」とにべもない。拍子抜けするほど単純なルールを守り、結果を出し続けるからこそ、世界中の投資家から尊敬を集めているのだ。ちなみにバフェット氏は贅沢(ぜいたく)を好まず、毎朝マクドナルドを食べ、一日5缶コーラを飲むという(それで92歳までバリバリ現役なのもスゴい)。収入は役員報酬の10万ドルのみで、58年に米国の地方都市に購入した家に今でも住み続けている。彼の投資哲学は人生哲学にも通じており、それもまた魅力のひとつだろう。■バフェットが次に手を伸ばす業種は?ここからは、バフェット氏の投資手法を詳しく見ていく。株式評論家の坂本慎太郎氏はこう語る。「彼がやっているのは、企業の将来像を見定めて、それに対して現在の株価が安ければ買うという手法。よく『バリュー投資』といわれますが、全然違うと思います。バリュー投資とは、企業が持っている資産や、毎年上げる利益と株価の比率を計算し、割安だったら投資する手法です。これに対して、バフェットが重視しているのは、その企業がこれから先、長きにわたって稼ぐ力。企業の現在を見るバリュー投資と、未来を見据えた上で、それをできるだけ安く買おうという彼の手法は、『安く買う』という点以外はむしろ正反対だといえます」しかし、それならバフェット氏はなぜ日本株に将来性を見いだしているのか? 経済アナリストの馬渕磨理子氏が解説する。「商社株はその典型例ですが、成長力があるのに気づかれず、株価が安く放置されている日本企業はいくつもあります。そうした優良企業を、ほかの人々が魅力に気づいていないタイミングで買うのが彼のスタイル。商社への追加投資も検討しつつ、それ以外にも伸びしろのある銘柄があると思ったからこそ今回来日したのでしょう」(馬渕氏)では、バフェット氏が次に狙う業種、企業はなんだろうか? 「商社は引き続き有望」と語るのは坂本氏。「商社というビジネス形態は日本特有で、海外の投資家にはなじみがありません。日本国内でも昔からある業態ということで、高収益、高配当なのに人気がありませんでした。商社は事業があまりにも多角化しているために、投資家は何を見て判断すればよいのかがわかりにくいのです。その結果、手がける事業の中でも一番株価が割安な業種である『資源セクター』(エネルギーや鉄鉱石などの関連企業)と同程度の水準で放置されていました。要は儲かっているのに、その収益性は長続きしないだろうとナメられていたわけです。バフェットはそこを見抜き、自分の投資によって商社の収益力が適切に評価され、株価が上がると踏んだはず。今後もその流れは続くでしょう」馬渕氏からは、バフェット氏がこれまで投資してきた企業のラインナップが参考になる、とのアドバイスをもらった。「バークシャーの資金量はなにしろ莫大です。自分の売買で株価が大きく振れてしまうような中小企業には投資できないので、誰でも名前を知っているような大企業を選ぶでしょう。バークシャーが米国で大きく投資しており、かつ日本国内に優良企業がある業種といえば、食品・銀行が代表的。ほかにも割安さや日本独自の強みが際立つ業種に注目しています」ここ1年ほど日本株は横ばいで、煮え切らない展開が続いているが、〝投資の神様〟の動きが起爆剤となってもおかしくない。
Microsoft Security があらゆるビジネスを包括的に保護 – News Center Japan
Security, Compliance and Identity 担当コーポレートバイスプレジデント バス ジャカル (Vasu Jakkal)
※本ブログは、米国時間 11 月 2 日に公開された “Protect your business with Microsoft Security’s comprehensive protection” の抄訳を基に掲載しています。
組織のセキュリティの確保や継続が容易だったことはありません。しかし、この 1 年間で、脅威の状況は大きく変化し、あらゆる業界のあらゆる規模の組織が大きな影響を受けています。サイバー攻撃の頻度と巧妙さは著しく増加しました。フィッシング詐欺やランサムウェアの被害に関するニュースが毎日のように報道されています。重要インフラや医療機関など、かつては「聖域」とみなされていた組織や機関が、悪意のある者のターゲットになることで人命に関わるリスクが増しています。
また、ハイブリッドワークが定着した中で、個人のデバイスが企業ネットワークの重要な部分となることによって攻撃対象が拡大・変化し、増加しています。私の周りの多くのセキュリティチームは、ビジネスのレジリエンスを高める方向へと戦略を変更しており、賢明なことに、その多くがゼロトラスト のアプローチを採用しています。これらのチームは、人々や組織を危険から守るために、舞台裏で確信を持ってたゆまぬ努力を続けています。そのようなスーパーヒーローたちを念頭に置きながら、本日は、Microsoft Security の最も包括的なセキュリティ、あらゆる規模の組織の成長、創造、革新の支援についてのエキサイティングなニュースを皆様にお伝えします。
あらゆる人を保護
サイバー攻撃者は差別なく攻撃します。中小規模企業も大企業と同様に被害に遭いやすいのです。しかし、マイクロソフトの調査によれば、中小規模企業の約 60 パーセントが、リソースの不足や専門的なセキュリティスキルの不足を理由として、安全なサイバーセキュリティを維持するための十分な体制が整っていないと回答しています1。本日発表する Microsoft Defender for Business は、今月末にパブリックプレビューが開始され、従業員数...